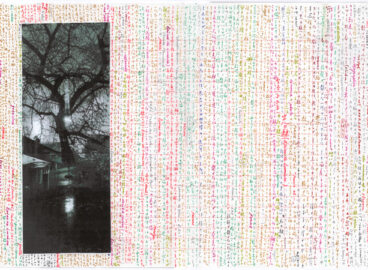吉増剛造インタビュー
一九六四年の第一詩集『出発』刊行以来、吉増剛造氏はたゆまぬ創作活動を続け、戦後の日本の詩の世界においてもっとも特異なアートフォームのひとつを創り上げてしまった。あまりにも風変わりで、時には活字化することすら難しく、時には声とともにパフォーマンスという形態を取らざるえなかった。それゆえに、吉増さんは異端児と看做されてきた節もあるが、詩というものの本質を探求する姿勢においては至極まっとうな道を歩んだともいえるだろう。60年代末からの現代美術やフリージャズとのコラボレーションをはじめ、80年代からは銅版に言葉を刻んだオブジェの制作、近年は写真作品や「gozoCiné」と名づけたビデオ作品も多数発表するなど、違ったメディアにも積極的に取り組んできた。現在七四歳にして、どん欲な制作意欲は一向に衰える気配がない。このインタビューは、二〇一二年一〇月一日、ある秋晴れの日、ニューヨークのダウンタウンのカフェ「ピンク・ポニー」にて行われた。吉増さんがギタリスト、ターンテブル奏者の大友良英氏と組んで北米五都市をパフォーマンスして回ったツアーを前日に終えたばかりだった。 2012年10月1日 吉増剛造インタビュー ニューヨーク、ダウンタウンのカフェ、ピンク・ポニーにて 恩田: 今日は六〇-七〇年代の日本の文化状況と吉増さんとの関わりについてお話しを伺おうと思います。吉増さんが処女詩集『出発』を刊行されたのは六四年ですね。ちょうど慶應義塾大学を卒業された頃でした。どんなことが日本では起こっていましたか? 六〇年安保闘争と学生生活 吉増: 六〇年安保闘争があって、その洗礼を受けながら学生生活を送っていました。ご存知のように六〇年代はアメリカニゼーションの時代といって間違いないと思いますけれども、その新鮮な波動が、文学としてはビート・ジェネレーション、歌声としてはボブ・ディラン、ジョーン・バエズらの歌声として響いてきて、しばらく遅れてビートルズが聞こえてきた。思い出しながらお話ししますけれど、僕の学生時代にビートの最もすぐれた紹介者だった諏訪優さんという人がいて…、詩人で、翻訳家で、優しい人だったのね。ギンズバーグの『Howl』や『Kaddish』を聴く会を頻繁に企画していました。東京で『Doin’』という雑誌を出し始めて、白石かずこさん、奥成達さん、草森紳一さん、岡田隆彦さん、沢渡朔さんたちが関わって、音楽、写真、詩が交じりあっていました。だから、その当時の先駆的な詩の状況はまずアメリカの最先端を紹介する諏訪優さんのまわりから始まっていました。詩と同時にジャズが入ってきた。ソニー・ロリンズ、ジョン・コルトレーン…。六〇年代の初めというのは同時多発的でしたね。もう一つの大きな流れは美術だった。その最先端には瀧口修造さんがいた。日本でのシュールレアリズム研究における中心人物だったけれども、人柄があの国の人と思えないくらい稀な人だった。元々は西脇順三郎先生のお弟子さんだったけれど、アナーキーというか、細心で、繊細で、深い…。磯崎新さん、荒川修作さん、武満徹さん、東野芳明さん、大岡信さんらがそのまわりに集まっていまいした。それから舞踏の土方巽さんもいた。寺山修司さんもいた。だから、そのころの最も大きな文化の中心を形成したのは瀧口修造星雲です。もちろん、美術を芯に据えての話しですが…。で、その次ぎの世代の人たちが、ハイレッド・センターの赤瀬川原平さん、中西夏之さん、高松次郎さん。さらに写真家の高梨豊さん、中平卓馬さん、森山大道さん、多木浩二さん。この人たちが一九七〇年に『プロヴォーグ』を創刊して写真史に足跡を残すことになります。それこそ“星雲”のようにして、日本の戦後の芸術運動を形成していた。生け花作家の中川幸夫さんや舞踏の大野一雄さんでさえ、この“星雲”のただ中にいたといえる。場所としては南画廊、東京画廊、新宿の椿近代画廊などがありました。そういった場所で美術の運動、文学の運動が重なっていた。 “アンダーグラウンド”のさらに底流のような流れ 恩田: なるほど。諏訪優もひとつの“星雲”だったんでしょうか? 吉増: いや、“星雲”というようないい方では捉えられないのね。むしろ、異端児ですね。英米文学の仲間からは随分と白い目で見られていたし、敵が多かったはずです。茨の道を歩んで早死にしたけども、この諏訪優さんという人を逃しちゃいけない。『Howl』と『Kaddish』を翻訳し、それからグレゴリー・コーソも翻訳したかな。練馬に住んでいて、英文学者の仲間は“練馬ビート”って悪口をいっていたけど、彼の果たした役割はとても大きかった。「詩の朗読運動」と「リトル・マガジン」を出していこうとする運動の中心人物で、 白石かずこさんがそこにいました。“アンダーグラウンド”のさらに底流のような流れでしたね。 恩田: 諏訪優と吉増さんの関わりあいはどういうものでしたか? 吉増: 六四年、処女詩集『出発』を出してすぐに、諏訪さんが僕の詩を読まれて、 『Subterraneans』の第二号に書かせてくれた。その雑誌は今でも大切に持っています。非常にインティメイトな、垣根をすーっと超えるような精神がその頃はあった。 恩田: ビートにせよ、安保にせよ、時代の雰囲気と合致したんでしょうか? 吉増: その頃だったと思いますが、ケネス・レクスロスも日本にやって来た。ビートの親代わりみたいな人でね。一世代前の野性的で大きなアメリカの詩人でした。それにつられて、まだ若かったギンズバーグや、ゲーリー・スナイダーも京都の南禅寺に来ていたかな。京都がいつも熱くて…。 恩田: そういうアメリカのビート詩人たちと接する機会があったんですね。 吉増: そう。それに、六四年にロバート・ラウシェンバーグがやって来て、草月会館ホールで「ボブ・ラウシェンバーグへの20の質問」というパフォーマンスをやりました。その結果が『金本位制 』 Gold Standardの作品です。その頃、東野芳明さんとか、飯島耕一さんとか、いわゆる東大の仏文科出の秀才たちがシュールレアリズムの研究会をつくっていたんだけど、その人たちの美術批評が東京の文化をひっぱり始めた。みんな瀧口星雲に属していました。 恩田: なるほど。面白いのは瀧口修造はもともとフランス文化とつながりがあって、その星雲のなかにアメリカ文化が入ってきたと。 吉増: ひとつの大きな道はね、マルセル・デュシャンだった筈です。デュシャンという人はフランスから亡命するようにしてニューヨークに来たじゃない。マックス・エルンストもそうだね。だからアメリカの一番先端的なものとフランスのそいうものの接点も無視できない。荒川修作さんもニューヨークに活動の拠点を置くようになったし。フランスの知識人たちがニューヨークへ動いて、フランス一辺倒ではなくなった。クロード・レヴィ=ストロースだってそう。そういう流れが瀧口さんとシュールレアリズムを中心とする日本の六〇年代の文化運動と連動していた。ただ、僕がその場で見ていたようにいっているけれど、ほとんどが雑誌からの知識や伝え聞きですけどね。こういうの苦手だなあ…。 恩田: 日本の知識人はフランス文化から学ぶうちに、その流れをフォローするうちにアメリカ文化というものを発見し、それを日本に輸入し始めたということでしょうか? 吉増: そういういい方で正しいと思います。 そんな古典的な土壌の中から、最も先端的な流れが生まれてきて、それが草月会館ホールだった 恩田: 草月会館ホールはどういう場所だったんですか? 吉増: 生け花の流派で保守的な池坊とか古流というのがあるじゃないですか。草月流は池坊から出てきたのかな。勅使河原蒼風さんという途方もない天才が流派を作って、その息子が勅使河原宏さんという映画作家だった。そんな古典的な土壌の中から、最も先端的な流れが生まれてきて、それが草月会館ホールだった。勅使河原さんのところは、資金もあるし、場所もあるから、一種の文化的な拠点になっていった。それから、当時は読売アンデパンダン展という大きな展覧会を読売新聞が運営していた。読売の文化部長だった海藤日出男さんが中心人物だったのね。そこからたくさんの才能のあるアーティストが出てきた。それが草月の運動とリンクして、瀧口さんのサークルもかぶってきていますね。 恩田: なるほど。その当時は美術も、文学も、舞踏も、他の分野も、何の垣根もなかったように聞こえるんですが…。 吉増: 今から考えると恐ろしいぐらい垣根がなかった。一九六八年頃のいい方の「解放区」です。詩の場合は、六〇年代初期の『凶区』の活動が画期的でした。天沢退二郎さん、鈴木志郎康さんたちのね。それに蠢くようにして、政治運動、歌謡曲、盛り場、美術批評、暗黒舞踏、ジャズのトポス、それから寺山修司さんと唐十郎さんの演劇運動。寺山さんも、唐さんも、土方さんを介して瀧口修造とつながっています。瀧口さんというのはね、温和で静かだったけど必ず現場に姿を見せていた。どんなにつまらいものでも、ちゃんと片隅で座って見てました。これは頭でっかちの批評家には真似できない。瀧口さんの一番弟子が武満徹さんでした。普通だったら自分の師匠に作曲家をまず第一に挙げるけれども、武満徹は瀧口さんを挙げる。それでわかるじゃない。荒川修作だって瀧口さんを挙げる。磯崎さんだってそうでしょうね。そういう芸術共同体の真ん中にいたのが瀧口さん。私製のパスポートを作って若い友人に差し上げるとか、遊びの精神のある人だったし、反骨の人でもあった…。 恩田: だからこそ違うジャンルの人を集められたんでしょうね。瀧口さん自身の仕事というのはどいうものでした? 吉増: 瀧口さんの代表的な書物は『近代芸術』ですけれど、シュールレアリストとしての存在というか立ち居振る舞いが実に根源的かつ全身的でした。ただ、瀧口さんは周囲から見れば美術評論家として神話的な人だったけれど、学問の世界やサークルの外からは胡散臭い人に見えたに違いないと思います。晩年にはデカマルコニーの制作に打ち込まれていましたね。 恩田: ちなみに瀧口さんのサークルと草月会館ホールの関わりあいはどういうものでしたか? 吉増:…